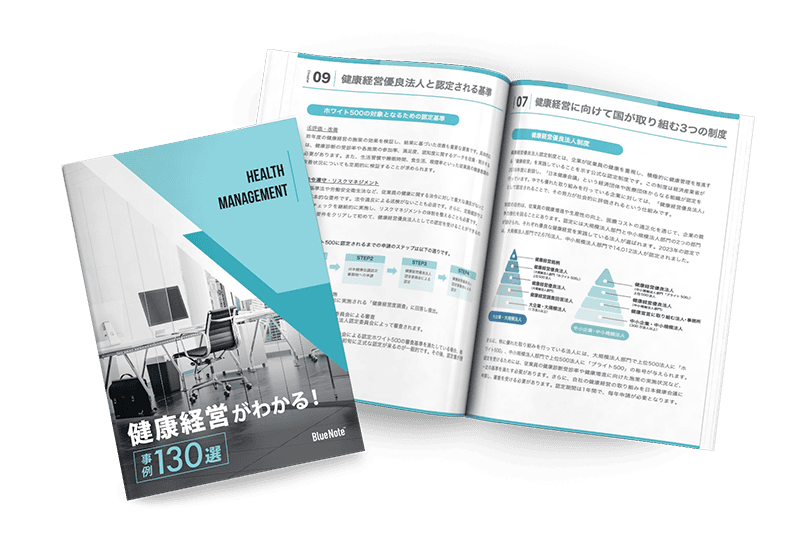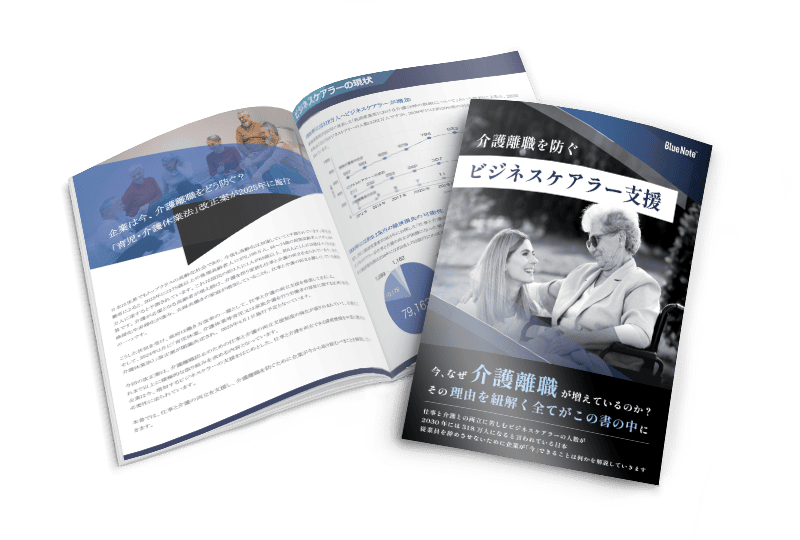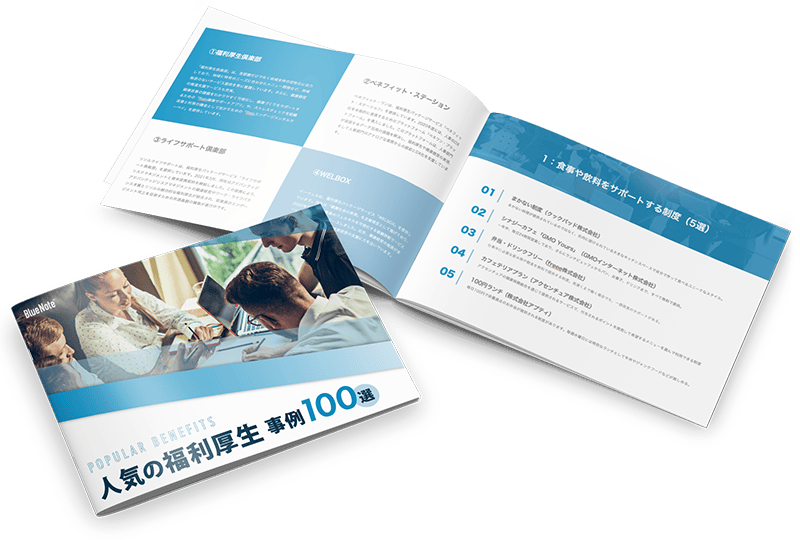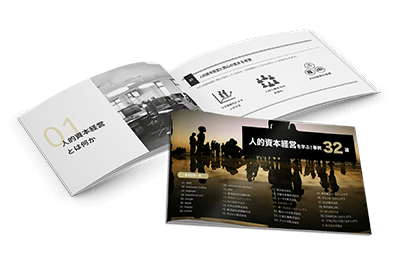「アンコンシャスバイアス」という言葉をご存知でしょうか。この言葉はあまり馴染みがないかもしれませんが、私たちの日常生活や職場における人間関係に大きな影響を与える要素です。多様性がますます求められる現代社会やビジネス環境において、この問題を理解しておくことは非常に重要です。無意識の偏見、つまりアンコンシャスバイアスは、企業の経営や管理にも悪影響を及ぼす可能性があります。
そこで今回は、この無意識の思い込みがどのように働くのか、アンコンシャスバイアスとは何か、具体的な例やその対策についてまとめました。
目次
●アンコンシャスバイアスとは●アンコンシャスバイアスは誰もが持つ無意識の思考
●アンコンシャスバイアスが注目される背景
●アンコンシャスバイアスの代表的な9例
・正常性バイアス
・集団同調性バイアス
・ステレオタイプバイアス
・確証バイアス
・アインシュテルング効果
・ハロー効果
・慈悲的差別
・インポスター症候群
・権威バイアス
●企業や職場で起こりがちなアンコンシャスバイアスの具体的なケース
・人材育成におけるバイアス
・人事採用におけるバイアス
・研修機会におけるバイアス
・人事配置におけるバイアス
・育児支援制度の利用におけるバイアス
●アンコンシャスバイアスを生み出す3つの原因
1:自己防衛としての「エゴ」
2:時代に合わない「習慣や慣習」
3:個人特有の「感情スイッチ」
●アンコンシャスバイアスが企業や組織に与える影響
・採用や評価などで公正な判断が難しくなる
・人間関係の悪化とパフォーマンスの低下
・組織の多様性を損なう危険
●アンコンシャスバイアス対応に取り組む5つの効果
1:マネジメントの質が向上する
2:ハラスメントの予防・防止につながる
3:ダイバーシティ&インクルージョンを推進する
4:多様な社員がその能力を十分に発揮できる
5:持続的な成長と業績向上に寄与する
●アンコンシャスバイアスの対応方法
・自社の状況を理解する
・知識を深める
・自覚と認識に努める
・研修を実施する
●まとめ
アンコンシャスバイアスとは
アンコンシャス・バイアス(無意識バイアス)とは、本人が気づかないうちに抱いている「ものごとの見方や捉え方の偏り」を指します。このバイアスは、個人の過去の経験や知識、価値観、信念によって無意識に認知や判断を行い、それが自然な言動として現れることがあります。自身ではその歪みを認識できず、「無意識の偏見」とも言われます。
日常のささいな発言や行動に潜むアンコンシャス・バイアスは、「単なる日常の出来事」として軽視されがちですが、それを放置すると社員の士気が低下したり、ハラスメントが増加し、職場のコミュニケーションが悪化することで、結果的に組織や個人のパフォーマンスにも悪影響を及ぼす恐れがあります。
実際にハーバード大学の研究では、履歴書の内容が同じでも、名前が男性的か女性的かによって選考結果に差が出ることが明らかになっています。
近年では、アンコンシャス・バイアスに関する理解や応対方法を習得することは、多様な人材を適切にマネジメントするために不可欠なスキルとされており、アンコンシャス・バイアスに対処するため、多くの企業がトレーニングを導入しています。特にGoogleやフェイスブック、マイクロソフトなどの国際的な企業が先駆けとなり、現在では様々な業種の日本企業でも研修が行われています。
アンコンシャスバイアスは誰もが持つ無意識の思考
アンコンシャスバイアスは、私たちが共通して持っている思考様式の一つです。この現象は決して特殊なものではなく、日常生活や職場においても頻繁に目にすることができます。アンコンシャスバイアスは、私たちの判断や行動に知らず知らずのうちに影響を与え、その結果として様々な偏見やステレオタイプが形成されてしまうのです。アンコンシャスバイアスは、個人的な経験や文化的背景、社会的規範などに影響を受けて形成されるため、完全に排除することは難しいとされています。
例えば、職業に対する固定概念は、アンコンシャスバイアスの代表的な例と言えます。「看護師」という言葉を聞くと、多くの人が女性の姿を思い浮かべるのに対して、「医師」と聞くと男性をイメージすることが多いでしょう。このように、特定の職業に対して性別や年齢、さらには人種などの属性に基づいた偏った考えを持つことは、誰にでも起こり得ることです。
しかし、現代社会では、性別に関係なく個人の能力や適性に基づいて職業を選択する機会が増えてきており、このようなステレオタイプは時代にそぐわなくなりつつあります。
さらに、同じ立場の人と接する際でも、年齢や性別、さらには外見によって接し方を変えたり、相手が自分と同じ見解を持っていると無意識に仮定してしまったりすることは、アンコンシャスバイアスの影響が色濃く表れた行動だと言えるでしょう。
アンコンシャスバイアスが注目される時代的背景
アンコンシャスバイアスが注目されるようになった大きなきっかけは、2010年代にアメリカの企業で従業員の人種・性別の偏りが問題視され、その原因としてアンコンシャスバイアスの存在が指摘されたことにあるといわれています。
実例として、Googleでは2013年からアンコンシャス・バイアスに関する教育活動を始め、従業員が偏見を認識し、多様性を重視する組織づくりを目指しています。この取り組みは、2010~2013年に検索エンジンの日替わりロゴ(Doodle)に登場した人物の62%が白人男性で、女性がわずか17%だったことが「偏りがある」と指摘されたことがきっかけです。
また、最近では日本でも「ダイバーシティ」や「インクルージョン」といったあらゆる属性を受容・尊重する考え方が重視される傾向にあり、働き方も多様化の一途を辿っています。2021年に経済産業省が発表した「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」では、アンコンシャスバイアスへの対応の必要性が言及されており、企業に対して従業員の意識改革や組織風土の改善を求めています。
アンコンシャスバイアスの代表的な10例
アンコンシャスバイアスにはさまざまな種類が存在します。ここでは、日常生活の中で特に起こりやすい代表的な10の例を取り上げて解説します。日常的に見られるアンコンシャスバイアスの典型例をまとめました。
・正常性バイアス
正常性バイアスとは、自分が直面している深刻な状況を認識せず、「まだ問題ない」とか「いつも通り」と思い込む心理的傾向のことです。このバイアスに基づく判断は、危機に対する対応を遅らせ、最終的に被害を拡大させるリスクがあります。
・集団同調性バイアス
集団同調性バイアスとは、自分が属する集団の意見に無意識に従う心理を示しています。このため、個人の判断が疎かになり、集団が誤った決定をしていても、声を上げることなくその流れに流されることがあります。人間は常にどこかのグループに所属しているため、このバイアスの影響を受け続けていると言えるでしょう。
・ステレオタイプバイアス
ステレオタイプバイアスは、特定の特徴を持つ対象に対して勝手に認識や特性を一般化する思考パターンを指します。「この職業は女性に向いている」や「この趣味は若者向き」といった先入観が、当てはまらない人々を無視してしまう危険があるため注意が必要です。
・確証バイアス
確証バイアスとは、自分にとって都合の良い情報のみを選んで受け入れ、逆に不都合な情報を排除する思考のことです。このバイアスの典型的な例は、未確定な事象を調査する際に、自分の予想を支持する証拠だけを収集する行為です。
・アインシュテルング効果
アインシュテルング効果とは、慣れ親しんだ考え方や視点を重視し、他の意見やアイデアを無視する傾向を指します。このため、新たな視点や革新的な意見が受け入れられず、成長の機会を逃す可能性があります。
・ハロー効果
ハロー効果は、好意的な印象を持つ相手の行動や能力を過大評価する傾向を表します。また、逆に悪印象を持つ相手に対しても過少評価を行ってしまいます。この心理的バイアスは公平な評価を妨げる要因となることがあります。
・慈悲的差別
慈悲的差別は、社会的弱者や立場の弱い人に対して過度な配慮を行うことです。たとえば、身体的に不自由な人を手助けしたり、女性に対して負担をかけさせないよう配慮する行為などがこれに該当します。こうした行為は、本人が望んでいない場合、不快感や逆差別と感じられることもあります。
・インポスター症候群
インポスター症候群は、自分の能力を過小評価し、成功を運や他人の助けのおかげと考えてしまう心理的な傾向です。このため、成果を上げても自分の力だと感じられず、成長のチャンスを逃してしまうことが多いです。優れた潜在能力を持つ一方で、それを活かしきれないことで、組織にも損失をもたらすことがあります。
・権威バイアス
権威バイアスは、高い地位にある人物の意見を無条件で正しいと信じる心理です。これにより、低い地位の人々が貴重な意見を述べても無視されることがあり、また専門家の意見を鵜呑みにしやすくなります。この結果、企業の革新の機会を逃したり、若い世代の士気を低下させる原因となることがあります。
企業や職場で起こりがちなアンコンシャスバイアスの具体的なケース
では、職場や企業でよく見られるアンコンシャスバイアスの具体例をいくつか挙げてみましょう。
・人材育成におけるバイアス
人材育成において、アンコンシャスバイアスが影響を与える典型的な例は、「女性は結婚・出産ですぐに退職する」という偏見に基づくキャリア目標の設定です。このような思い込みは、女性に重要な仕事や長期プロジェクトへの参加を避けることにつながり、結果として従業員のモチベーションが低下し、期待される成長が見込めない可能性が高くなります。さらに、例えば、「外国人従業員は英語を使う業務しかできない」と考えるバイアスも問題です。このような固定観念は、外国人従業員の潜在能力を活かせないまま、限定された役割に押し込めることになります。
・人事評価におけるバイアス
人事評価でも、アンコンシャスバイアスが多く見られます。例えば、「人柄が好きだから」といった個人的な好感に基づく評価や、「以前のイメージで評価を下す」ようなケースがあります。新たに評価に値する成果を出したにもかかわらず、それ以前のミスやイメージで評価を下すことは、バイアスによる不当な人事評価の典型です。
・人事採用におけるバイアス
採用プロセスでも、アンコンシャスバイアスが影響を与えることがあります。出身大学や前職などの情報は重要な基準となる一方で、選考担当者のバイアスの対象にもなりやすいです。例えば、「この大学の出身なら優秀に違いない」と学歴だけで採用を決定することは、結果的に入社後のミスマッチを生み出す可能性があります。また、「体育会系のサークル出身だから、根性があるだろう」と思い込み、採用することもバイアスの典型です。
・研修機会におけるバイアス
研修の機会も無意識のバイアスの影響を受けることがあります。「若手社員はキャリア初期だから学ぶ必要があるが、ベテラン社員は経験が豊富だから研修は必要ない」などの思い込みがその一例です。しかし、経歴や年齢に関わらず、全ての社員がスキル向上や知識習得の機会を持つことは、組織全体のイノベーションと競争力を高めるために不可欠です。
・人事配置におけるバイアス
人事配置においても、アンコンシャスバイアスが不当な判断を生み出すことがあります。例えば、従業員の年齢や性別などの業務内容に無関係な属性を理由に、特定の仕事や昇進をさせないといった人事が問題です。業務や役職を任せる際には、あくまで仕事に関連のある能力を基準として、公平に配置を行うことが重要です。さらに、「子育て中の女性は管理職に登用しづらい」と考えるバイアスも、女性のキャリアアップを妨げる要因となります。
・育児支援制度の利用におけるバイアス
育児支援制度の利用に関してもバイアスが影響を及ぼすことがあります。「育児休業は女性が取得するもの」という固定観念により、男性社員の育休取得が暗に制限されるケースがあります。
厚生労働省の調査によると、2022年度の男性の育児休業取得率は18.2%にとどまっており、この数字からもジェンダーに関するバイアスの影響が見て取れます。
アンコンシャスバイアスを生み出す3つの原因
アンコンシャス・バイアスを生み出す要因は大きく3つに分類されます。これらの要因は、人が無意識に特定の考えや行動を取る背景として働き、特に職場や日常生活で偏見や誤った判断を引き起こす原因となります。それぞれの要因を理解することで、バイアスを意識的に抑え、公平で多様性を尊重した環境づくりに役立てることができます。
では、その3つの要因について詳しく見ていきましょう。
1. 自己防衛としての「エゴ」
人は自分自身を守ろうとする本能があります。自分の行動を正当化したり、良い印象を与えようとしたりするのは、心地よい状態を維持するための自己防衛の表れです。この「エゴ」が、無意識の偏見を生み出す一因となっています。
2. 時代に合わない「習慣や慣習」
長年慣れ親しんだ習慣や、常識だと思い込んでいることが、時代の変化に伴って適合しなくなることがあります。多様性が増す社会において、これらの慣習にずれが生じているにも関わらず、気づかずに言動をとり続けると、違和感やストレスを与えてしまいます。特に、同質性の高い組織では注意が必要です。
3. 個人特有の「感情スイッチ」
「感情スイッチ」とは、その人特有のこだわりや劣等感、不安感などを刺激するポイントのことです。これが刺激されると、本能的に自己防衛反応をとったり、冷静でいられなくなったりします。その結果、他者や現実を客観的に見ることができなくなり、時には攻撃的な言動につながることもあるのです。
アンコンシャスバイアスが企業や組織に与える影響
アンコンシャスバイアスは、職場の意思決定や人間関係に影響を及ぼし、組織運営に悪影響を与えることがあります。無意識の偏見がどのように組織に問題を引き起こすのか、具体的な弊害についてまとめました。
・採用や評価などで公正な判断が難しくなる
管理職や上司がアンコンシャス・バイアスに影響を受けると、公正な人事評価や採用が妨げられることがあります。例えば、特定のミスを犯した従業員に対して、将来的な評価が不利になる場合や、最近の成果のみで能力を過大評価する現象が見られます。こうした偏見は、従業員の不満を増し、モチベーションの低下や離職につながる可能性もあります。また、採用においても、「子育て中の女性は管理職に登用しづらい」や「転職が多いから忍耐力がない」といった偏見により、優秀な人材を見逃すリスクがあります。
・人間関係の悪化とパフォーマンスの低下
アンコンシャス・バイアスを持った従業員がコミュニケーションに臨むと、組織の人間関係が悪化する可能性があります。特に、年齢や性別に対する無意識の偏見は、日常の態度や会話に自然と表れます。「子どもの発熱で男性従業員が早退するのはおかしい」や「ゆとり世代は忍耐力がない」といったネガティブな発言が原因で、職場の人間関係が悪化し、業務での意思疎通に支障をきたし、パフォーマンスが低下する恐れもあります。
・組織の多様性を損なう危険
現代の経営環境では、多様な人材が活躍できる環境づくりが重要です。LGBTQや外国人雇用の機会が増える中で、アンコンシャス・バイアスを放置すると、大きなトラブルや組織力の低下を招く可能性があります。また、SNSなどによる拡散リスクもあり、人種や宗教、性別、文化に関する差別的な発言により、社会的な信用を損なう恐れもあります。アンコンシャス・バイアスを認識し、対策することで、多様な視点を取り入れてイノベーションを促進し、組織の競争優位性を維持することが重要です。
アンコンシャスバイアス対応に取り組む5つの効果
アンコンシャス・バイアスへの取り組みは、組織に前向きな変化をもたらしています。特に「制度や施策は整っているのに、期待した効果が得られない」といった課題を抱える組織にとって、この取り組みは現状を打破し、新たな成果を引き出すきっかけとなるでしょう。バイアスへの理解を深めることで、組織全体の生産性やチームワークの改善が期待できます。
他にもどんな効果が期待できるか、まとめていきます。
1. マネジメントの質が向上する
アンコンシャス・バイアスを認識し、それに対処することで、管理職やリーダーはより公正で客観的な意思決定を行うことができます。バイアスが意思決定プロセスに与える影響を理解し、組織のミッションや価値観に基づくリーダーシップを実践することで、組織全体の信頼と透明性が向上します。これにより、より健全で効果的なマネジメントスタイルが育まれます。
2. ハラスメントの予防・防止につながる
多くのハラスメントの背景には、無意識の偏見が潜んでいます。アンコンシャス・バイアスを意識的に排除しようとする取り組みは、このような不適切な行動や文化を見過ごさず、防止するための重要なステップとなります。バイアスを意識し、取り組む職場では、全ての従業員が敬意を払い合う文化が築かれ、ハラスメントの予防が徹底されます。
3. ダイバーシティ&インクルージョンを推進する
アンコンシャス・バイアスに取り組むことで、職場環境は多様性と包摂(インクルージョン)の価値をより深く理解することができます。これにより、従業員一人ひとりが安心して意見を発し、個々の違いが尊重されるインクルーシブな職場が形成されます。すべての従業員が心理的安全性を感じられる環境は、結果として、組織における創造性と革新性を大いに促進します。
4. 多様な社員がその能力を十分に発揮できる
無意識のバイアスが排除されることで、異なる背景やスキルを持つ従業員がその才能を最大限に発揮できる場が提供されます。バイアスなしに評価されることで、人材の公平な機会が確保され、社員それぞれが自分らしさを持ちながら貢献できる環境が整います。これにより社員のエンゲージメントが高まり、個々の成長へとつながります。
5. 持続的な成長と業績向上に寄与する
長期的に見ると、アンコンシャス・バイアスへの取り組みは、組織全体の持続可能な成長や業績の向上に寄与します。偏見に捉われずに人材を活用する組織は、多様な視点を取り入れることができ、新しい市場のニーズに迅速に対応する力を養うことができます。これが結果として、競争優位性の確立と維持を可能にします。
アンコンシャスバイアスの対応方法
最後に、アンコンシャスバイアスへの具体的な対策についてまとめていきます。アンコンシャスバイアスは、無意識の心理的作用によって誰もが陥る可能性があるものです。組織においては、これを個々人の問題ではなく、全体の課題として認識することが重要です。
どのようにしてバイアスを認識し、組織や個人として向き合っていくべきか、実践的な方法を紹介します。
・自社の状況を理解する
アンコンシャスバイアスが組織内でどのように影響を与えているかを理解することが第一歩です。各個人が自身の考えや行動を絶対視している場合、問題として認識することが難しくなります。そこで、組織全体でアンコンシャスバイアスについての教育やディスカッションの場を設けることが重要です。具体的な問題や将来起こり得るトラブルについても話し合うと、より効果的な対策が立てられます。
・知識を深める
アンコンシャスバイアスの基本的な知識をしっかりと理解することが必要です。アンコンシャスバイアスとは何なのか、どのような形で現れるのか、そしてどのような影響を与えるのかを知ることで、予防と自覚的な解消に役立ちます。例えば、ステレオタイプバイアス、ジェンダーバイアス、正常性バイアスなど、具体的なバイアスの種類とその影響を学ぶことが重要です[2][3][4].
・自覚と認識に努める
知識を得た後は、自分自身や組織のメンバーがアンコンシャスバイアスを抱いていないかを意識的に確認することが重要です。自身の行動や言動を振り返り、無意識の思い込みに基づいた判断や言動がないかをチェックすることが大切です。例えば、メモを取る方法を用いて、自分の思考のクセに気付くことも有効です。
・研修を実施する
社内でアンコンシャスバイアスに対する意識が芽生えたら、具体的な研修やセミナーを実施することが推奨されます。研修では、自身が抱く偏見と向き合う時間を設けたり、少数派について理解する時間を設けたり、具体的な事例から適切な対応を学ぶことができます。外部の研修資料や講師を活用することも有効で、客観的かつ体系的な知識を身につけることができます。
まとめ
アンコンシャスバイアスは、私たち全員が持っている無意識の思い込みや偏見です。これは人間の脳が効率的に情報を処理するために自然と身についた仕組みであり、必ずしも悪いものではありません。しかし、特に企業や組織において、このバイアスが適切にマネジメントされていないと、人材の採用や評価、職場環境に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
重要なのは、アンコンシャスバイアスの存在を認識し、その影響を最小限に抑える努力をすることです。そのためには、まず自社の現状を正確に把握し、全社員がアンコンシャスバイアスについての理解を深めることが必要です。また、定期的な研修の実施や、意思決定プロセスの見直しなど、具体的な対策を講じることも重要です。
アンコンシャスバイアスへの適切な対応は、単なる問題解決以上の価値があります。それは組織の多様性を促進し、社員一人一人の能力を最大限に引き出すことにつながります。結果として、企業の持続的な成長や競争力の向上にも寄与するのです。
これからの時代、多様性を尊重し、一人ひとりの能力を最大限に引き出せる組織づくりは、今や企業の競争力の源泉といえるでしょう。私たち一人ひとりが自身のアンコンシャスバイアスに向き合い、克服していくことが、今後ますます求められていくはずです。
ぜひ本コラムを参考に、自身のアンコンシャスバイアスを振り返ることから始めてみてください。